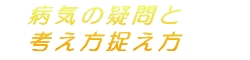怱晄慡偺帯椕
仴媫惈怱晄慡偺帯椕
媫惈怱晄慡偼媫寖偵怱晄慡徢忬偑弌偨忬懺偱丄尦乆枬惈怱晄慡偑偁偭偨応崌偲怱憻昦偑側偔媫寖偵敪徢偟偨応崌偺
2捠傝偑峫偊傜傟傑偡丅
媫惈怱晄慡偱偼丄婎慴幘姵傊偺懳墳丄寣峴摦懺偺夵慞偵傛傞徢忬偺寉夣傪栚巜偟傑偡丅
寣峴摦懺夵慞偺偨傔偺栻暔椕朄偼丄棙擜栻(儖乕僾棙擜栻丄hANP)丄徤巁栻丄嫮怱栻(僇僥僐乕儖傾儈儞)傪梡偄傑偡丅
傑偨媫惈怱嬝峓嵡屻偵偼丄ACE慾奞栻偑怱憻儕儌僨儕儞僌偵懳偟偰桳岠偱偁傞偙偲偑峀偔抦傜傟偰偄傑偡丅
栻暔椕朄偱傕寉夣偟側偄応崌偵偼丄曗彆弞娐偺IABP傗PCPS傪峫椂偟傑偡丅
仴枬惈怱晄慡偺帯椕
崅寣埑丄嫊寣惈怱幘姵丄怱嬝徢側偳偺條乆側弞娐婍幘姵偺椪彴宱夁偺壥偰偵怱婡擻掅壓傪惗偠丄
枛徑庡梫憻婍偺巁慺廀梫検偵尒崌偆偩偗偺寣塼検傪攺弌偱偒側偔側偭偨昦懺偱丄惗妶偵巟忈傪棃偨偟偨忬懺
偱偡丅
帯椕偼QOL偺夵慞偲惗柦梊屻偺夵慞偵偁傝傑偡丅
枬惈怱晄慡偺帯椕偱偼丄怘帠椕朄丄塣摦椕朄丄栻暔椕朄偑峴傢傟傑偡丅
怘帠偲偟偰偼嵶朎奜塼検偺憹壛傪杊偖偨傔偵墫暘惂尷偑廳梫偱偡丅
塣摦椕朄偼姵幰偺忬懺偵崌傢偣偰峴偄傑偡丅
栻暔椕朄偼ACE慾奞栻丄兝僽儘僢僇乕偑拞怱偵側傝傑偡丅
ACE慾奞栻偲兝僽儘僢僇乕偼枬惈怱晄慡偺姵幰偺梊屻傪夵慞偝偣偨僄價僨儞僗偑偁傝傑偡丅
偦偺偙偲偼戞103夞堛巘崙壠帋尡偵傕弌戣偝傟偰偄傑偟偨丅
亙ACE慾奞栻亜
怱晄慡偱偼RAA(儗僯儞仺傾儞僊僆僥儞僔儞仺傾儖僪僗僥儘儞)宯偑槾恑偟傑偡偑丄
偙傟偼丄傾儖僪僗僥儘儞嶌梡偵傛傞嵶朎奜塼検偺曐帩仺慜晧壸偺憹戝丄
傾儞僊僆僥儞僔儞偺嶌梡偵傛傞寣娗廂弅仺屻晧壸憹戝丄
傪摫偔偨傔丄寢壥偲偟偰怱晄慡傪憹埆偝偣傑偡丅
ACE慾奞栻偼丄傾儞僊僆僥儞僔儞嘥仺傾儞僊僆僥儞僔儞嘦偺曄姺峺慺偱偁傞ACE傪慾奞偟丄
RAA宯偵傛傞埆弞娐傪抐偮偙偲偑偱偒丄寢壥偲偟偰慜晧壸丄屻晧壸偲傕偵寉尭偝偣丄惗柦梊屻傪夵慞偟傑偡丅
傑偨丄怱憻儕儌僨儕儞僌偵懳偟偰ACE慾奞栻偑桳岠偱偁傞偲偄偆曬崘偑偁傝傑偡丅
偟偐偟ACE慾奞栻偼恡婡擻偑旕忢偵埆偄応崌(僋儗傾僠僯儞抣亜3.0mg/dl)傗椉懁惈恡寣娗惈崅寣埑偱偼丄
桝弌嵶摦柆偺抩娚傪棃偨偡偨傔偵巺媴懱撪埑偑媫寖偵掅壓偟堦嫇偵恡婡擻偑埆壔偡傞偙偲偑偁傞偨傔偵巊偊傑偣傫丅
椪彴揑偵偼丄ACE慾奞栻偱恡婡擻埆壔傪傒偨応崌偵偼恡寣娗惈崅寣埑傪媈偆昁梫偑偁傝傑偡丅
亙兝僽儘僢僇乕亜
兝僽儘僢僇乕偼奼挘宆怱嬝徢(DCM)偱桳岠惈偑擣傔傜傟偨屻丄偦偺懠偺枬惈怱晄慡偱傕桳岠惈偑擣傔傜傟偨僄價僨儞僗偺
偁傞栻偱偡丅
怱憻偵偁傞兝1庴梕懱傪僽儘僢僋偟怱攺悢傪尭彮偝偣傞偙偲偱怱嬝晧壸傪尭傜偟傑偡丅
傑偨丄恡憻偵偁傞兝庴梕懱傪僽儘僢僋偡傞偙偲偱儗僯儞暘斿傪梷惂偟丄ACE慾奞栻偲摨條偵
懱塼挋棷傗寣娗廂弅傪梷惂偡傞岠壥傕偁傞傛偆偱偡丅